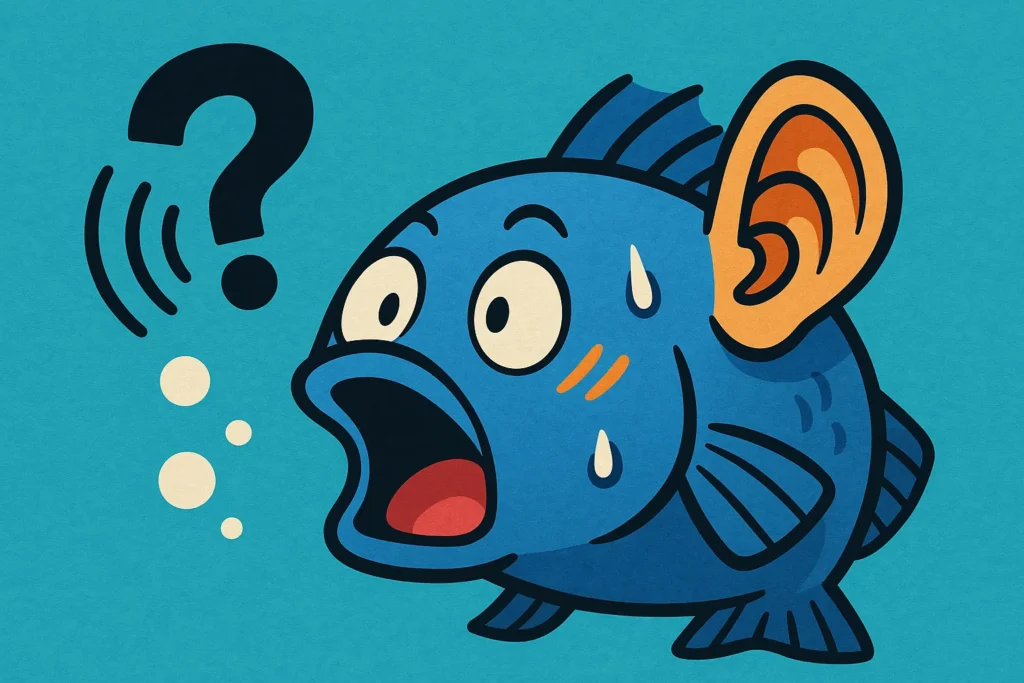
もくじ
はじめに
魚の世界は“静か”だと思っていませんか?
でも実は、魚たちは音を聞いて、感じて、行動しているのです。
しかもその耳は、私たちのように外には見えません。
「耳がないのに、どうやって聞いているの?」
そんな疑問から、今回のブログが始まります。
本記事では、
- 魚の耳の場所としくみ
- 水中で音がどう伝わるのか
- 魚が音で何を感じ、どう行動しているのか
を、やさしく、わかりやすく解説していきます。
第1章 魚にも耳はある?“見えない耳”の場所とつくり
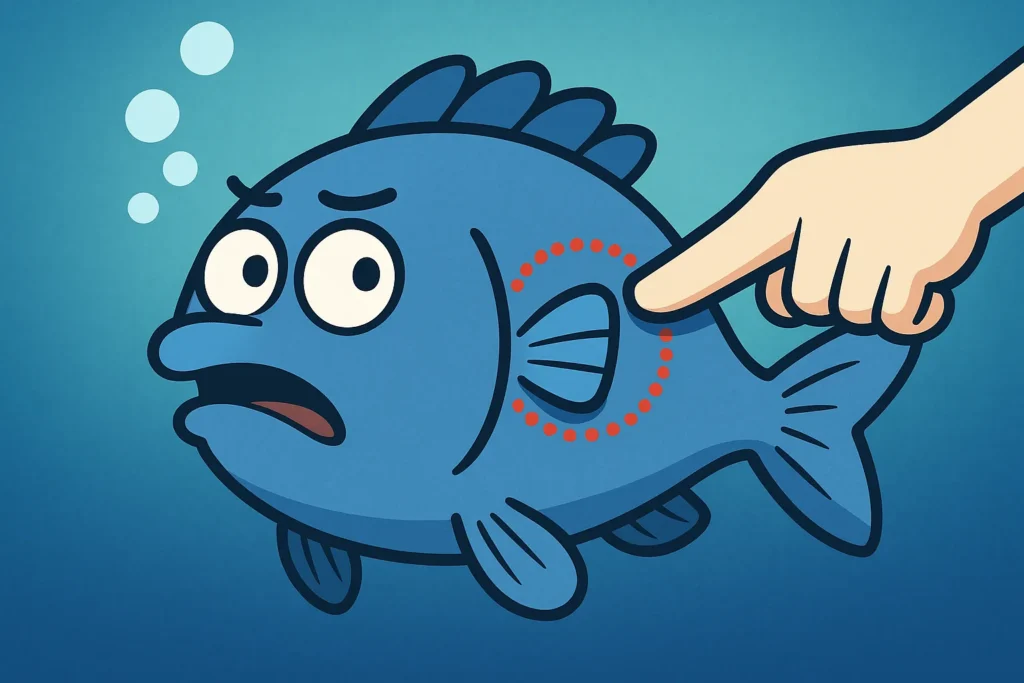
「魚に耳ってあるの?」
水槽の中を泳ぐ魚を見ても、犬や猫のような“耳らしい耳”は見当たりません。
ですが――実は魚にも、ちゃんと耳があります。
ただしそれは、私たちのような“外に出ている耳”ではなく、頭の中に隠れている「内耳」だけの耳なのです。
魚の耳は“中にある”だけ
人間の耳は、「外耳」「中耳」「内耳」の三段構造になっていますが、
魚の耳は、外耳も中耳もなく、“内耳だけ”でできているというシンプルな構造です。
魚の内耳は、頭の奥、脳の下あたりにあり、主に次のようなパーツで構成されています:
- 耳石(じせき):石のような小さな結晶体。振動を感知する
- 感覚毛(かんかくもう):細かい毛のような細胞。揺れや傾きをキャッチ
- 半規管(はんきかん):体のバランスを保つための器官
これらのしくみで、魚は音を感じ、位置や動きを把握しているのです。
「耳石」は音の振動をとらえるカギ
魚の内耳にある「耳石」は、実はとても重要な働きをしています。
水の中では、音は空気中よりも速く・遠くまで伝わるため、
体全体が揺れたり、音波の振動を受けたりします。
耳石はまわりの組織よりも比重が重いため、振動の伝わり方がズレます。
そのズレを感覚毛が感じ取ることで、「音が聞こえた」「揺れた」ことを判断できるのです。
耳がないように見えても、魚たちは体の奥深くでしっかり音を“感じて”いるんですね。
音だけでなく、バランス感覚も耳でキャッチ
さらに、魚の内耳は平衡感覚(バランス)を保つ役割も果たしています。
泳ぐときに上下左右に傾いたり、回転したときの動きを察知して、体の向きを調整するのです。
人間でいう「三半規管」にあたる部分があり、水中でも安定した泳ぎを可能にしています。
「魚に耳はない」と思っていた方も、実は見えないだけで、
私たちと同じように“聞いて”“感じて”“バランスを取っている”ことがわかってきたのではないでしょうか?
次章では、魚がどのように水の中で音を受け取り、どうやって聞き分けているのか?
水中ならではの“音の伝わり方”について深掘りしてまいります。
第2章 魚はどうやって音を聞く?水中の音の伝わり方

魚の耳が「内耳だけ」だということは、前章でご紹介しました。
では、実際に水中ではどのように音が伝わり、魚たちはそれをどうやって“聞いて”いるのでしょうか?
私たちの住む空気の世界とは違う、水の中ならではの音の伝わり方と、魚の“聞こえ方”のしくみに迫ってみましょう。
水中の音は「速く」「遠く」まで伝わる
まず知っておきたいのが、水中の音は空気中よりも早く、遠くまで届くという特徴です。
- 空気中の音速:約340メートル/秒
- 水中の音速:約1,500メートル/秒(約4.4倍!)
つまり、水中では音が非常に効率よく伝わるため、遠くの出来事や小さな音も魚たちは感じ取ることができるのです。
魚の体全体が「音を感じるアンテナ」に
魚は、耳だけでなく、体そのものでも音や振動を感じています。
とくに重要なのが、側線(そくせん)と呼ばれる感覚器官です。
側線とは:
- 魚の体の側面に走る線のような器官(頭から尾まで)
- 水の流れや振動をとらえるセンサーのような働き
- 他の魚の動き、水のうねり、障害物の存在なども察知できる
この側線のおかげで、目で見えない音や動きを感じ取り、周囲の状況を把握しているのです。
胴体の骨も“音の共鳴器”になる
中には、魚の種類によっては骨や浮き袋(うきぶくろ)を使って音をより敏感に感じる能力を持っているものもいます。
特に、「ウェーバー器官」と呼ばれる特別な構造を持つ魚(コイやナマズの仲間など)は、
浮き袋が音の振動をキャッチし、その振動が小さな骨を通じて内耳に伝えられます。
これにより、より広範囲の音域を聞き分けることができるのです。
魚が“聞いている”音とは?
魚は人間と同じように「声」として音を聞いているわけではありませんが、
以下のような音や振動をしっかり認識し、行動に活かしています:
- 他の魚の泳ぎや尾びれの動き
- 捕食者の接近する水の振動
- 人が水面をたたく音や餌を落とす音
- 川や海の流れ、波の衝撃
このように、魚たちは水の中で起きている“音の風景”を全身で感じ取り、生きるための判断材料にしているのです。
目に見えない音の世界で、魚たちは実に繊細に周囲と向き合っています。
次章では、そんな音の情報を使って、魚たちが実際にどう行動しているのか?
音がもたらす行動の変化や、記憶・学習との関係についてご紹介してまいります。
第3章 魚は音でどう行動する?音とふるまいの関係
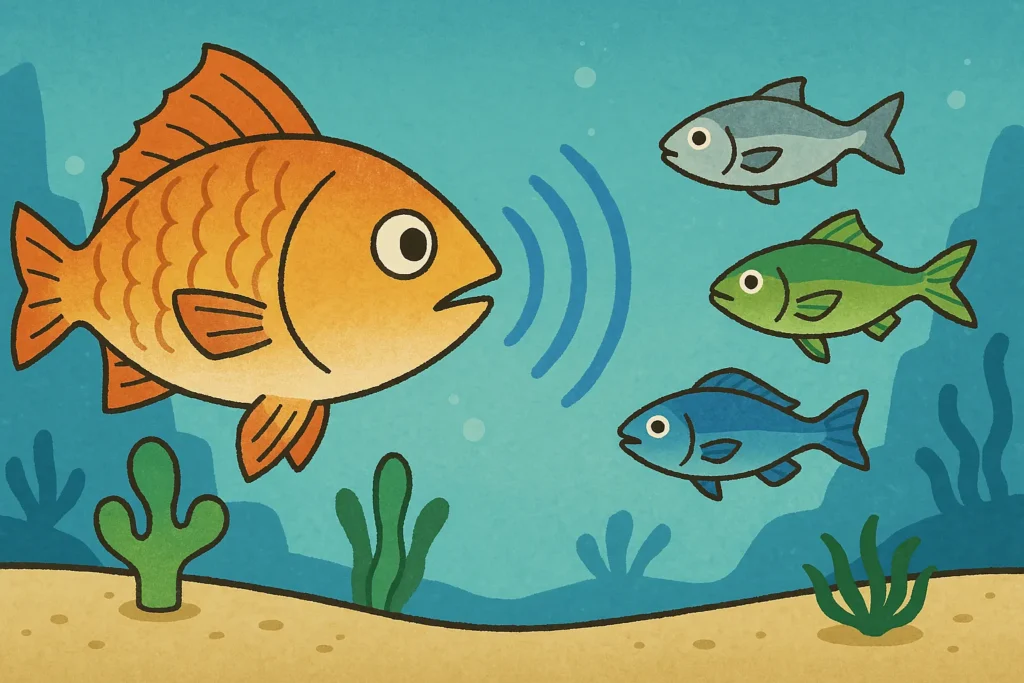
魚が水中で音を感じていることは、これまで見てきたとおりです。
では、その音の情報をもとに、魚たちは実際にどのような行動を取っているのでしょうか?
この章では、音が魚の行動に与える影響や、魚たちが“音を使って学ぶ”姿をご紹介していきます。
音に反応する魚たち
多くの魚は、音や振動に非常に敏感に反応します。
たとえば…
- 水面にエサを落とすと、すぐに集まってくる
- 水槽をノックすると、驚いて逃げる
- 飼い主の足音や食器の音に反応して泳ぎ出す
これらはすべて、魚が音のパターンを“記憶”し、“学習”している証拠です。
特に金魚やコイは、飼育下でも「特定の音でエサがもらえる」と覚えることで知られており、
数週間後でもその音に反応する行動が確認されています。
音でコミュニケーションする魚もいる
魚の中には、“音を出す”ことでコミュニケーションをとる種類も存在します。
- オスがメスを呼ぶために音を出す
- なわばりを守るために“警告音”を鳴らす
- 集団で泳ぐ際に位置を知らせ合う
たとえば「ハタ類」や「イシモチ類」は、
筋肉や浮き袋を振動させて「ブンッ」「ポンッ」といった低音を発し、仲間や相手に意図を伝えるとされています。
これはまさに、魚同士の“音声による会話”といっても過言ではありません。
騒音が魚に与えるストレス
一方で、人工的な騒音は魚にストレスを与える原因にもなります。
- 船のエンジン音
- 港湾工事の重機音
- モーター音やドリル音などの低周波振動
これらの音は、水中では私たちの想像以上に広がり、
魚にとっては「逃げるべき危険」や「警戒すべき環境」として認識されてしまうことがあります。
ストレスによって:
- エサを食べなくなる
- 群れから離れて行動する
- 繁殖行動をやめてしまう
といった変化が見られることもあり、水中の“音の汚染”が魚たちの生活に与える影響は無視できません。
音は魚にとって「見る」「嗅ぐ」と同じぐらい大切
魚たちにとって、音とは単なる“雑音”ではなく、
生きるための情報そのものであり、行動を決める重要な手がかりです。
- 音を聞いて敵を避ける
- 音を頼りに仲間と泳ぐ
- 音を覚えてエサの時間を予測する
- 音で意思を伝え合うことすらある
私たちが考える以上に、魚たちは「音の世界」をしっかりと生きているのです。
次の「おわりに」では、この“見えないけれど確かにある魚の聴覚の世界”を、やさしく振り返りながらまとめてまいります。
水の中の「静けさ」の中にある“音の存在”に、きっと気づけるはずです。
おわりに 音を感じる魚たち、水の中にも“声”がある
魚の世界は静か。
そう思っていた方も、今回のブログを通して、水の中にもたくさんの“音”があること、そして魚たちがその音をしっかりと感じ、活用していることに驚かれたのではないでしょうか。
外に耳が見えなくても、
声を出して話すわけではなくても、
魚たちは**「音を聞き、音で行動し、時には音で通じ合っている」**のです。
- 内耳で振動を感じ
- 側線で水の流れを読み
- 音に反応して泳ぎ、逃げ、集まる
- 自分から音を出して、仲間や敵に意思を伝える
そんな魚たちの姿には、静かで奥深いコミュニケーションの世界が広がっていました。
次に水族館や川、海で魚を眺めるとき、
彼らが「聞いている」ことに少し思いを巡らせてみてください。
私たちには聞こえなくても、
水の中ではたしかに、魚たちの“声”が響いているのかもしれません。
これからも、魚の体のしくみや行動、知られざる魅力をやさしく解き明かしていきます。
また次回のブログも、どうぞお楽しみに。
魚忠ECサイトのご紹介
魚たちが音を感じ、静かな水の中で豊かに暮らしていることを知ると、
その命の恵みをより丁寧に、やさしく味わいたくなりますね。
魚忠は、創業70年以上の老舗魚屋。
職人が一つひとつ丁寧に仕込んだ漬け魚・焼き魚を、冷凍で全国へお届けしています。
- 焼くだけ・温めるだけで簡単
- 骨取り済みで食べやすい
- 贈り物にもご好評いただいています(お中元・お歳暮にも)
魚をもっと身近に、もっと手軽に楽しむなら、魚忠のオンラインショップをのぞいてみてください。
▶公式オンラインショップはこちら:
https://uochu.base.shop/
