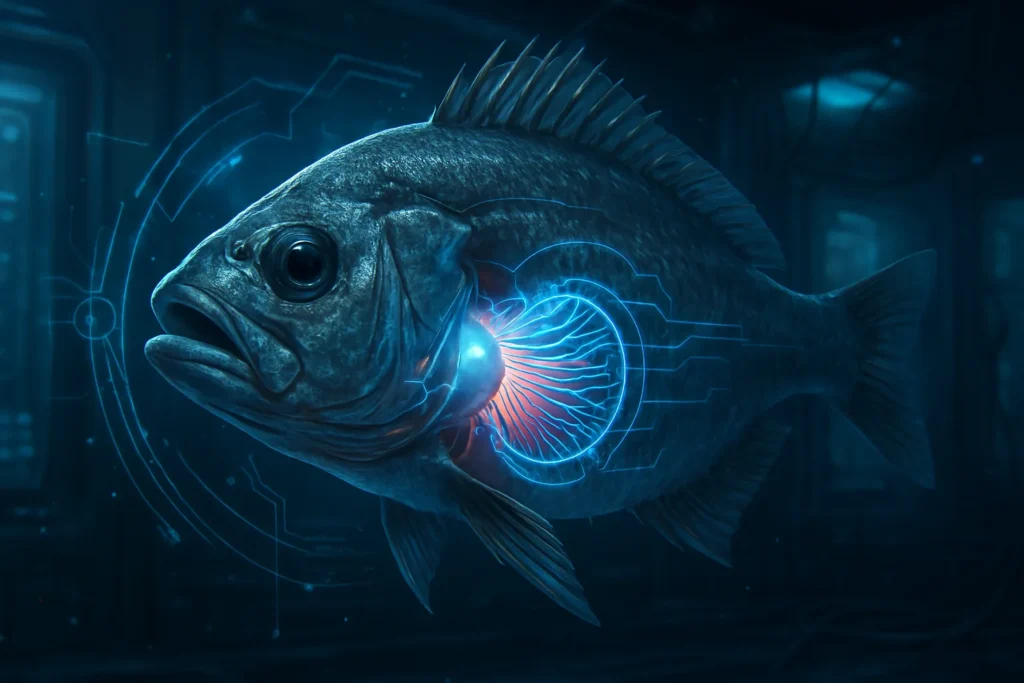
もくじ
はじめに
私たち人間は、鼻や口から空気を吸って肺で呼吸をしています。
では、水の中に生きる魚たちは、どうやって“息をしている”のでしょうか?
「魚にはエラがある」とはよく聞きますが、
エラってどこにあるの?どうやって空気を取り込むの?人間の呼吸と何が違うの?…と考えていくと、意外と知らないことばかりです。
今回のブログでは、
- 魚が呼吸するしくみ
- エラの構造と働き
- 種類によって異なる呼吸方法
- 呼吸にまつわるちょっとした豆知識
など、魚の「息」にまつわるふしぎと仕組みを、やさしく・しっかり解説していきます。
第1章 魚はなぜ水中で息ができるの?呼吸の基本とエラの役割
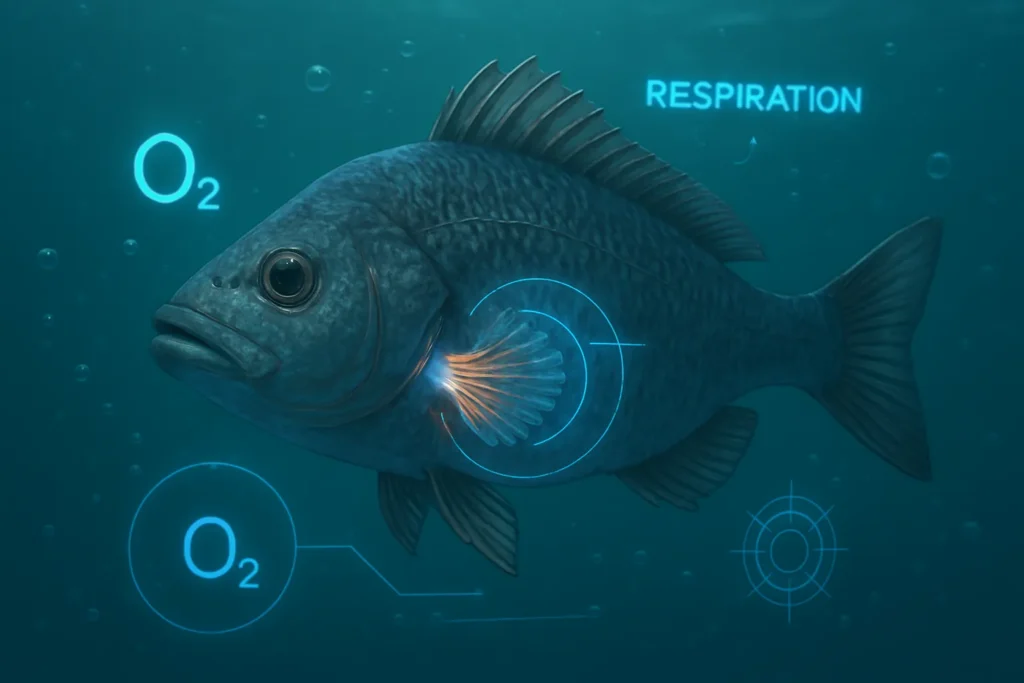
私たち人間は、空気を吸って肺で呼吸をしています。
では、水の中で暮らす魚は、どうやって酸素を取り入れて生きているのでしょうか?
魚は水の中で呼吸するために、肺の代わりに「エラ(鰓)」という器官を使っています。
このエラが、魚にとって命を支えるとても重要な役割を果たしているのです。
水の中にも酸素はある?
まず大前提として、水の中にも酸素は存在します。
ただし、私たちが吸っている空気に含まれる酸素(約21%)と比べると、
水に溶けている酸素(溶存酸素)はごくわずかです。
たとえば、気温20℃、真水の場合、1リットルの水に含まれる酸素は約9ミリグラム程度。
空気に比べてはるかに少ないため、魚はそのわずかな酸素を効率よく取り出す必要があるのです。
肺ではなく「エラ」で呼吸する理由
水中では、空気を肺に取り込んで呼吸するのは効率が悪いため、
魚は体の外に開いた器官「エラ」で直接水中の酸素を取り込む仕組みを進化させてきました。
エラにはたくさんの毛細血管が張り巡らされており、
水に溶けた酸素が、エラの表面を通じて血液に取り込まれるようになっています。
そして、二酸化炭素も同時に排出される。
つまり、エラは肺と同じく「ガス交換の場」というわけです。
魚の呼吸の流れ(基本のプロセス)
魚の呼吸は、次のようなステップで行われています:
- 口を開けて水を吸い込む
- 吸い込んだ水は口の奥からエラへと流れる
- エラの膜(鰓弁)を通る間に、水中の酸素が血液に取り込まれる
- 呼吸の終わりに、水はエラぶたの後ろから排出される
この流れを魚は休むことなく、反射的に繰り返しています。
まさに、“生きるためのポンプ運動”ともいえる動きです。
「エラぶた」は呼吸のゲート
エラは外から見ると、魚の頭の左右にある「エラぶた(鰓蓋)」の内側に隠れています。
このエラぶたが開閉することで、水の流れを作り、酸素の取り込みを助けているのです。
じっと魚を観察すると、口がパクパクし、エラぶたが開いたり閉じたりしている様子が見えます。
これは、まさに魚が呼吸をしている証拠なのです。
水中という厳しい環境の中で、わずかな酸素を効率よく取り込む――
そのために魚たちは、非常に優れた「エラ」という器官を手に入れたのです。
次章では、このエラがどういう構造になっていて、
なぜ水から酸素を取り出すことができるのか? そのしくみをさらに深く見ていきましょう。
第2章 エラの構造と仕組み:水から酸素を取り出す巧みなシステム
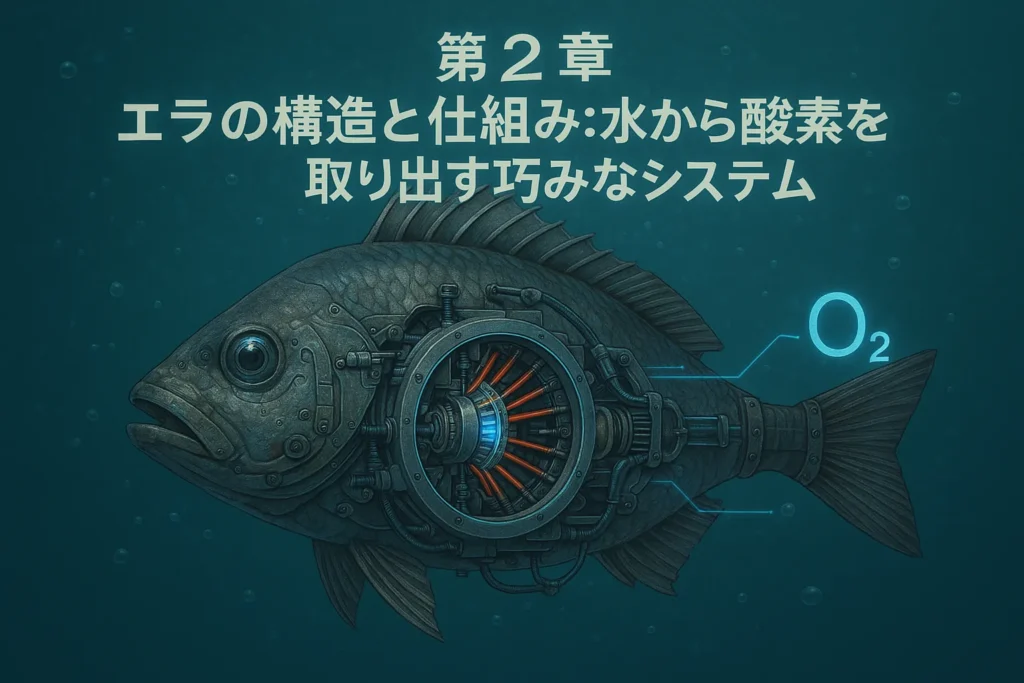
第1章では、魚が水の中で呼吸できる理由として「エラの存在」と「水中の酸素」をご紹介しました。
この章では、さらに一歩進んで、エラの構造や酸素を取り出す仕組みそのものを詳しく解説していきます。
一見シンプルに見える魚の呼吸ですが、その中には非常に効率的で巧妙なメカニズムが隠されているのです。
エラはどんな形をしている?
魚のエラは、外からは見えにくいですが、エラぶたの中には細くて柔らかいひだのような構造(鰓弁・さいべん)が並んでいます。
これが鰓弓(さいきゅう)という骨格構造に沿って、数対ずつ左右に配置されています。
エラの基本構成:
- 鰓弓(さいきゅう):エラの骨組み
- 鰓弁(さいべん):呼吸に使われる薄いひだ
- 鰓耙(さいは):水中のゴミを濾し取るフィルター的な構造
エラ弁は非常に薄く、そこには無数の毛細血管が張りめぐらされています。
この薄い膜と血管のネットワークこそが、水から酸素を吸収するためのカギなのです。
魚の呼吸に欠かせない「対流交換(たいりゅうこうかん)」
魚のエラがすごいのは、「対流交換(カウンターカレント)」という効率的なガス交換の仕組みを使っているところにあります。
これは、
- 水の流れ(酸素が多い)
- 血液の流れ(酸素が少ない)
が、逆方向に流れることによって、常に酸素を取り込み続けられるという仕組みです。
この仕組みのメリット:
- 酸素の濃度差を最大限に活用できる
- 水に含まれる少ない酸素でも効率的に吸収できる
- 魚が無駄なく酸素を取り込める
空気中より圧倒的に酸素が少ない「水中」でも生きていけるのは、
この対流交換のしくみによって、呼吸効率が非常に高められているからなのです。
「動かずに呼吸できる魚」「泳ぎ続けないと呼吸できない魚」
実は、すべての魚が同じように呼吸しているわけではありません。
魚の種類によっては、呼吸方法に大きな違いがあります。
エラぶたで呼吸できる魚(多くの一般的な魚):
- 口とエラぶたを動かすことで水流を作り、止まっていても呼吸可能
- タイ、アジ、サバなどが代表
常に泳ぎながら呼吸する魚:
- マグロやカツオなどの高速回遊魚は、自力でエラを動かす能力が弱いため、泳ぎながら水を口に流し込んで呼吸します
- 止まると酸素が取り込めず、「泳ぎを止めたら窒息してしまう」と言われるほど
このように、魚の呼吸方法は生活スタイルと深く結びついているのです。
エラは“究極の省エネ呼吸器”
エラは、非常に薄い構造でありながら、酸素を効率的に取り込み、二酸化炭素を排出するという高性能なガス交換装置です。
しかも、水の流れに逆らわず、むしろ活用して呼吸を助ける構造になっています。
限られた酸素を最大限に利用し、余計なエネルギーをかけずに生きる。
魚のエラは、まさに「省エネで命をつなぐ進化の結晶」といえるでしょう。
次章では、さらに魚ごとの呼吸の違いや、環境(水温や酸素濃度)によって呼吸がどう変わるのか、
そして“肺を持つ魚”というちょっと意外な存在にも注目していきます。どうぞお楽しみに。
第3章 魚の呼吸はこんなに奥深い!種類ごとの違いや環境との関係
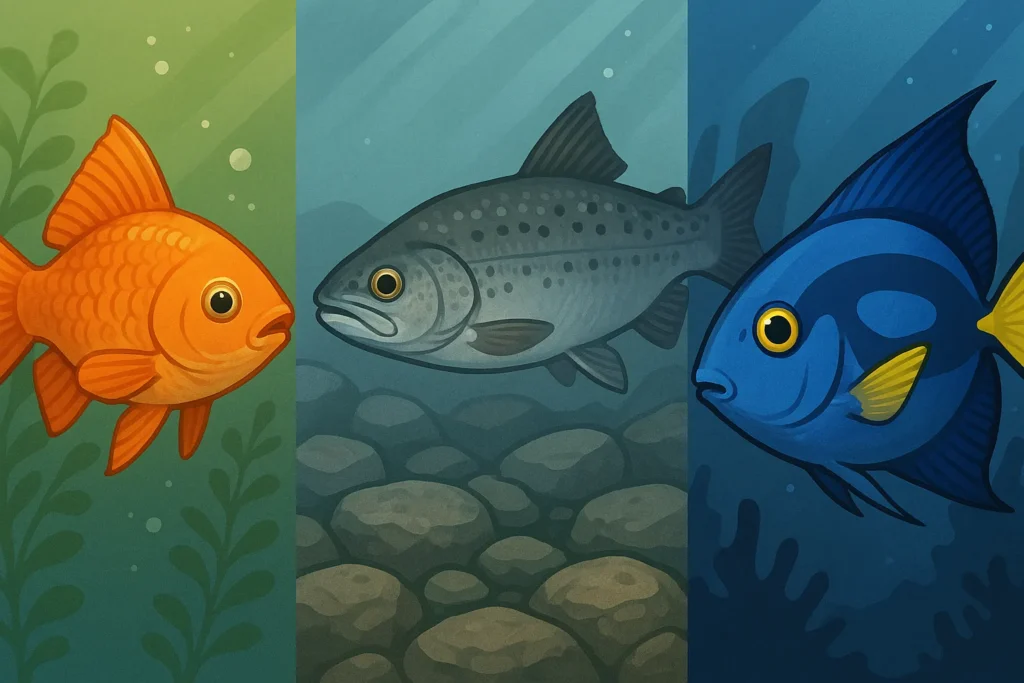
魚は「エラで呼吸する」と一口に言っても、実はその呼吸のスタイルは魚の種類や暮らす環境によって大きく異なるのです。
魚たちは、水温・酸素量・水質といった自然の条件に合わせて、呼吸のしかたを進化させてきました。
この章では、魚の多様な呼吸戦略と、それを支える体の仕組みを解説していきます。
泳ぎ続けて呼吸する魚、止まっても呼吸できる魚
前章でも触れたように、魚の呼吸法には大きく2タイプあります。
① ポンプ式(口とエラぶたを動かす)
→ 止まっていても呼吸できる
→ 多くの一般的な魚(タイ、アジ、ヒラメなど)
② ラム式(泳いで水を取り込む)
→ 泳ぎ続けないと酸素が取り込めない
→ 回遊魚(マグロ、カツオ、サメの一部など)
泳ぎ続けて水を流し込む方式は、筋肉量の多い高速泳法の魚に特有のものです。
この違いは、魚の生活スタイルそのものを決定づけています。
水温が呼吸に与える影響
水の温度が上がると、水中に溶け込める酸素の量は減ってしまいます。
つまり、水温が高いほど、魚にとって呼吸しにくくなるのです。
夏場に魚が元気をなくす、水面で口をパクパクさせる…
そんな行動は、水中の酸素不足に対応しようとしている証拠です。
また、養殖や観賞魚の世界では、水温と溶存酸素の関係をとても重視します。
- 水温が上がる→酸素が減る→魚のストレス増加
- 酸素不足→呼吸数の増加→疲弊・病気に弱くなる
このように、呼吸と環境は密接に結びついているのです。
酸素が少ない水域に対応した“特別な呼吸法”
一部の魚は、酸素の少ない環境でも生き延びる特別な工夫を持っています。
● 空気呼吸ができる魚
- ナマズ類やアナバス(ラビリンスフィッシュ)は、水面から空気を吸い込んで肺に似た器官で呼吸します。
- 泥の中や酸素の乏しい沼地でも生き延びる力を持っています。
● 肺を持つ魚(肺魚)
- アフリカや南米などに生息する肺魚(はいぎょ)は、なんと本当に“肺”を持っており、空気中から酸素を取り込むことができます。
- 乾季には泥に潜って“夏眠”し、空気呼吸で生き延びます。
● 皮膚呼吸をする魚
- 一部のウナギ類は、湿った皮膚から酸素を吸収することもできると言われています。
- 陸上を移動できるウナギやドジョウがいるのも、この性質があるからです。
呼吸が魚の「すみか」を決めている
呼吸のしやすさは、魚の“暮らす場所”や“行動範囲”にも直結しています。
- 酸素が豊富な清流には、ヤマメやイワナなどの活発な魚
- 酸素が少ない沼地や池には、ナマズやフナなどの特殊な呼吸能力を持つ魚
つまり、呼吸のしくみを知ることで、その魚がどんな環境でどう暮らしているのかが見えてくるのです。
魚の呼吸は単に「生きる手段」ではなく、
生息地・行動・進化・個性すべてにかかわる重要なテーマです。
次章では、このブログのまとめとして、魚の呼吸を通じて見える「生き方」や「自然への適応力」についてやさしく振り返っていきます。
おわりに 呼吸を知ると、魚の生き方がもっとおもしろくなる
私たちが普段あたりまえに接している魚たち。
ですが、彼らの「呼吸の仕組み」を知ると、そこには水中という環境に見事に適応した進化の知恵と、命をつなぐための工夫があふれていることがわかります。
- 空気の100分の1以下しか酸素がない水の中で、
- エラという精密な器官を駆使して、
- わずかな酸素をムダなく取り込み、
- 種類によっては、泳ぎ続けることで命をつなぎ、
- またある種は、水がなくても“空気”で呼吸できるように進化してきた。
魚の呼吸は、「生きるための当たり前」ではなく、環境に応じて磨かれた命の工夫のかたちです。
そして、それは魚たちの住む場所、動き方、性格までも形づくっている――
そう考えると、魚という生き物が一層魅力的に感じられてきませんか?
次に魚を見かけたとき、「この魚はどうやって呼吸してるんだろう?」と少し思いを巡らせてみてください。
きっと今までと違った視点で、水の中の世界が見えてくるはずです。
今後もこのブログでは、魚の知られざる魅力や豆知識、生活に役立つ情報をやさしく楽しくお届けしてまいります。
どうぞお楽しみに。
魚忠ECサイトのご紹介
魚の呼吸のしくみを知ると、水の中で生きるということがいかに繊細で、工夫に満ちた営みかが見えてきます。
そんな魚たちが届けてくれる“おいしさ”もまた、自然の恵みそのもの。
魚忠は、創業70年以上の老舗魚屋。
職人が仕込んだ漬け魚や焼き魚を、味噌や西京味などの味付けで丁寧に仕上げ、冷凍で全国にお届けしています。
- 骨取り済み、調理済みで焼くだけ・温めるだけ
- ご自宅用はもちろん、贈り物にも人気です
水の中で育った命の美味しさを、手軽に、安心して食卓へ。
どうぞ一度、魚忠の味をご家庭でお楽しみください。
▶オンラインショップはこちら:
https://uochu.base.shop/
