
もくじ
はじめに
「魚はおいしいけど、さばいたときのにおいがちょっと苦手…」
「台所に残る“あのにおい”、どうにかならないかな?」
そんな風に思ったことがある方、多いのではないでしょうか。
魚は私たちの食卓に欠かせない食材ですが、「におい」だけはどうしても敬遠されがちです。
けれど、そのにおいには“ちゃんとした理由”と“正しい対処法”があるのです。
今回のブログでは、
- 魚のにおいの正体は何なのか?
- なぜ魚はにおうのか?どの魚がにおいやすい?
- 家庭でできるにおい対策と処理のコツ
をやさしく、わかりやすくご紹介します。
第1章 魚のにおいって何が原因?成分と発生のしくみ
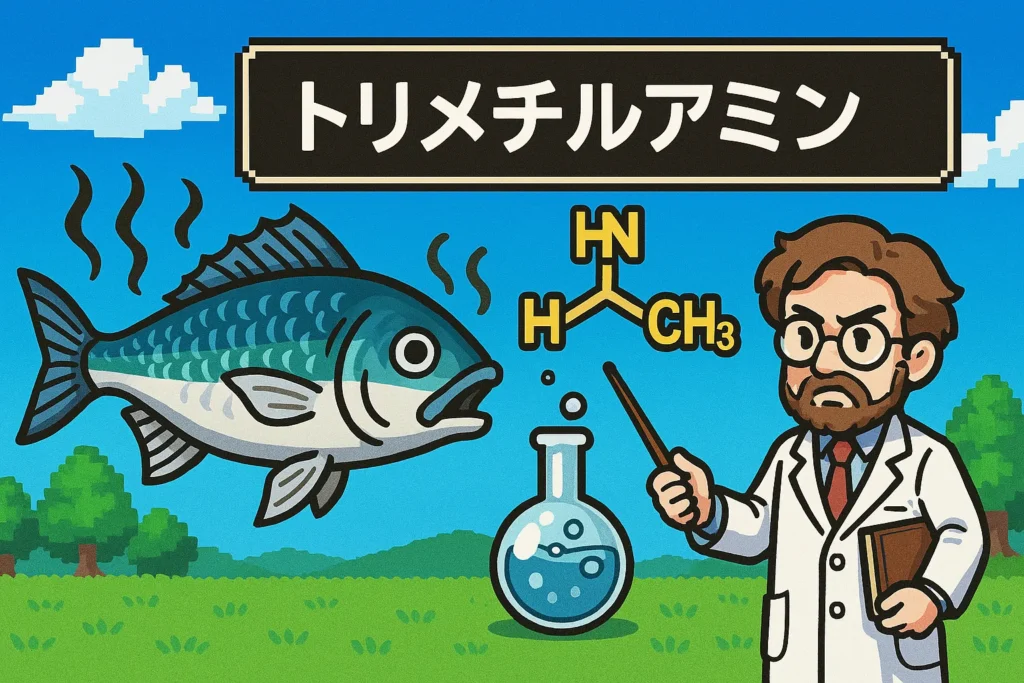
「魚のにおい」と聞いて、どんなにおいを思い浮かべますか?
生ぐささ、ヌメリのようなにおい、焼いたあとの煙っぽいにおい…。
実は、それらのにおいの正体には、いくつかのはっきりとした原因物質があるのです。
この章では、魚のにおいを生む成分と発生のしくみについて、わかりやすく解説していきます。
魚の「生ぐささ」は“トリメチルアミン”が主な原因
魚のにおいの元として、最も知られているのが
「トリメチルアミン(TMA)」という成分です。
これは、魚が海水中で取り込んだ「トリメチルアミンオキシド」という物質が、魚の死後に分解されて生まれる揮発性の成分です。
時間がたつとこのTMAが増えていき、生ぐささが強く感じられるようになります。
▶つまり、「時間がたった魚ほど、においが強くなる」理由はここにあるのです。
ヌメリのにおいは“菌とたんぱく質”の分解によるもの
魚をさばくときに気になるあの「ぬるぬる」。
あれは魚の表面を保護するための粘液ですが、時間がたつと細菌が増えて、ぬめりが強くなり、においも出てきます。
このにおいの元は、魚の表面にあるたんぱく質やアミノ酸が分解されてできる硫黄化合物など。
いわゆる「腐敗臭」に近いにおいで、古くなった魚ほどこのにおいが強く感じられます。
焼いたときの“香ばしいにおい”にも実は科学的な理由が
一方、魚を焼いたときのにおいは、脂肪分とアミノ酸が加熱によって変化した香気成分によるものです。
これは「焼き魚の香ばしさ」として、むしろ“おいしさ”の一部とされるにおいですね。
ポイントは、生臭さとはまったく別のメカニズムで生まれているということです。
魚のにおいは「鮮度」と「保存状態」で変わる
魚のにおいは、その魚自体の種類や脂の量にもよりますが、
それ以上に大きく影響するのが「鮮度の良し悪し」と「保存の仕方」です。
- 水分が多く菌が増えやすい
- 低温で管理されないと、分解が進みやすい
- 開きや内臓処理を怠ると、においの元が残る
このような理由から、正しく扱われた魚ほど、においが少ないというわけです。
次章では、「なぜ魚はにおいやすいのか?部位・種類・鮮度との関係」について、もう少し詳しく見ていきます。
日ごろの魚選びや調理にも役立つヒントが満載です。どうぞお楽しみに!
第2章 なぜ魚はにおいやすいのか?部位・種類・鮮度との関係
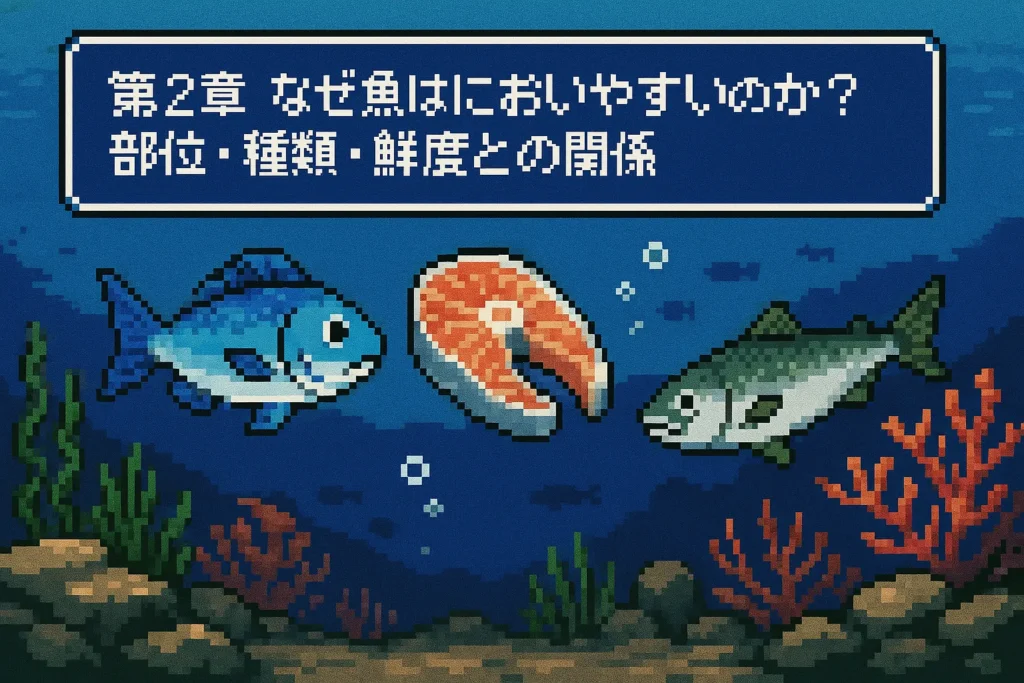
魚のにおいには原因物質があることはわかりましたが、実際にどんなときに、どの魚が、どの部位からにおいやすくなるのか?
それを知っておくことで、におい対策や魚選びにも自信がつきます。
この章では、「魚のにおいやすさ」に関わる3つの視点(部位・種類・鮮度)から解説していきます。
① 魚の“どの部分”が特ににおいやすい?
においの原因となる成分は、魚全体にありますが、特に強くにおいが出やすい部位がいくつかあります。
・内臓(特に胃や腸)
消化中の食べ物が残っているため、分解が早く、強いにおいの原因になります。
鮮度が落ちると、アンモニア臭や腐敗臭が出やすいです。
・血合い(赤黒い身の部分)
栄養が豊富な部位である一方、酸化しやすく、生ぐささの元になりやすい部分です。
特に青魚(サバ・イワシなど)に多く含まれます。
・皮と表面の粘膜
ここにも微生物や菌がつきやすく、ヌメリや独特のにおいが出てくる部分です。
表面を水でよく洗う、こすり取ることである程度軽減できます。
② 魚の“種類”によってにおいの出やすさが違う
においの強さには、魚の種類も大きく関係しています。
これは、魚の脂質(脂の量)や、生活する環境の違いによるものです。
においやすい魚の例:
- 青魚(サバ、イワシ、アジなど)
→ 脂が多く、血合いも豊富。酸化しやすく生ぐささが出やすい。 - 深海魚(アンコウ、メヒカリなど)
→ 水圧や低温に対応するため、特殊な体液を持っていて独特のにおいが出やすい。 - 汽水域の魚(ハゼ、ボラなど)
→ 川と海が混ざる場所にいる魚は、底の泥のようなにおいがつくことも。
においが少なめの魚:
- 白身魚(タイ、カレイ、ヒラメなど)は比較的においが少なく、初心者にも扱いやすい種類です。
③ 鮮度が落ちるほどにおいは強くなる
これは言うまでもないことかもしれませんが、においと鮮度は深く関係しています。
魚は死後、時間がたつにつれて
- 酵素による自己分解
- 細菌の繁殖
- たんぱく質や脂肪の酸化
が進み、さまざまなにおい物質が発生するようになります。
特に常温放置や、不適切な冷蔵・冷凍によって、見た目はきれいでもにおいが強くなることがあるため注意が必要です。
においの強さ=魚の“扱い方の難しさ”
においやすい魚は、それだけ取り扱いに注意が必要な魚とも言えます。
ただし、きちんと処理して新鮮なうちに調理すれば、美味しさに変わる脂と旨みを持っている魚ばかりです。
つまり、「においが強い魚=避ける魚」ではなく、
**「においの正体を知って、上手につきあえば、むしろ魅力が引き出せる魚」**なのです。
次章では、家庭でできる魚のにおい対策について、調理の前・最中・あとで分けて、実践しやすい方法をご紹介します。
日々の台所が快適になるヒントが満載ですので、ぜひご覧ください。
第3章 魚のにおいは防げる!調理前・中・後の対策まとめ

魚は新鮮でも、処理の仕方や扱い方次第でにおいが強く感じられてしまうことがあります。
しかし逆に言えば、ちょっとした工夫やポイントを押さえれば、においはかなり軽減できるのです。
この章では、調理の前・調理中・調理後の3つの場面に分けて、すぐに実践できるにおい対策をご紹介します。
【調理前】においを出さない下処理のコツ
魚のにおいを抑えるには、「最初の一手」がとても大切です。
1. ぬめりをしっかり取る
- 表面の粘膜にはにおいの元が多く含まれます。
- 塩をふって5分ほど置き、ぬめりを浮かせてから水で流すと効果的です。
2. 内臓と血合いを丁寧に処理
- 特に血合い(赤黒い部分)や内臓の残りカスは腐敗しやすく、においの原因に。
- 小さなスプーンや流水を使って、しっかり洗い流しましょう。
3. 水気をよく拭き取る
- キッチンペーパーなどで水分を丁寧に取るだけでも雑菌の繁殖を抑え、におい防止につながります。
【調理中】においを抑えながら、香りも楽しむ
調理中のにおいも、工夫次第で“香り”に変えることができます。
1. 薬味や香味野菜と一緒に調理
- 生姜、ねぎ、大葉、みょうがなどの香味野菜は、魚のにおいを中和し、爽やかな香りをプラスしてくれます。
- 味噌や酒、みりんもにおいのマスキング効果があります。
2. 焼き魚はしっかり予熱したグリルやフライパンで
- 低温からじわじわ焼くと、魚の脂が酸化してにおいが出やすくなります。
- フライパンならクッキングシートを敷いて調理すると、煙や焦げつきも減らせます。
【調理後】においを残さない片付け&換気のポイント
魚のにおいは、食べたあとも残りやすいので、すぐに対処しましょう。
1. 使った道具はすぐ洗う
- グリルや包丁、まな板などは、熱めのお湯と中性洗剤で早めに洗うのがコツ。
- グリルのトレイにはあらかじめホイルを敷いておくと掃除が簡単です。
2. においのこもった空気はしっかり換気
- 調理中から換気扇をまわしておくと、室内ににおいがこもりにくくなります。
- 調理後は窓を開ける、空気清浄機を使うのも有効です。
3. 手や服についたにおいは…
- レモン汁や酢水で手を洗うと、生臭さがやわらぎます。
- においがつきにくい服(ナイロンエプロンなど)を着用するのもおすすめです。
においを気にせず魚を楽しむためには、
「ちょっとした手間」と「基本の工夫」をセットで続けることがポイントです。
次章では、魚の扱いに慣れていない方にもおすすめの、魚忠の漬け魚シリーズをご紹介します。
においの悩みを減らしながら、美味しさはそのまま。手軽に魚を楽しみたい方にぴったりです!
第4章 魚忠の商品は“におい対策”も万全!手軽さと美味しさの両立
「魚を食べたいけれど、調理のにおいが気になる…」
「魚は好きだけど、下処理や後片付けが大変そう…」
そんな方にこそおすすめなのが、魚忠の漬け魚・焼き魚シリーズです。
創業70年以上の老舗魚屋・魚忠が仕立てる商品は、においへの配慮と、プロの味付けが両立しているのが魅力です。
においの元になる工程を、あらかじめカット
魚忠の商品はすべて、プロの職人が下処理・味付け・漬け込みを済ませた状態で冷凍されています。
- 内臓処理・血抜き済み
- 丁寧に骨を除去(骨取り済み商品あり)
- もろみや西京味噌などでしっかり下味
つまり、ご家庭では「焼くだけ・温めるだけ」でOK。
においの原因となる処理を行う必要がなく、台所ににおいが広がるのを大幅に抑えることができます。
味噌やもろみで香ばしく、においも“香り”に変わる
魚忠の漬け魚は、味噌・もろみ・西京などの発酵調味料でじっくり漬け込んでいます。
これにより、魚特有のにおいは抑えられ、焼いたときには食欲をそそる香ばしい香りが立ちのぼります。
- 生臭さ → 発酵のまろやかさ
- におい → 食欲をそそる“香り”へ
においが気になりにくいどころか、**魚が焼ける香りで「ごはんが進む」**という声も多く寄せられています。
忙しい日にも、安心して使える魚のおかず
- 解凍して焼くだけのシンプルさ
- 冷凍庫にストックできて、必要なときにすぐ出せる
- 骨が少なく、お子様や高齢の方にもやさしい
魚忠の商品は、魚に不慣れな方でも“失敗なし”で美味しく仕上がるのが特徴です。
▶公式オンラインショップはこちら
https://uochu.base.shop/
次章では、魚のにおいを「避けるもの」から「理解して対処するもの」へと前向きに捉え直す、まとめと振り返りをお届けします。魚との付き合いがきっと少し変わるはずです。
おわりに 魚のにおいを知れば、もっと美味しくつきあえる
魚を調理するときに感じる“におい”。
これまで何となく「気になるもの」「苦手なもの」と思っていた方も、今回のブログを通じて、においの正体と上手な向き合い方を知っていただけたのではないでしょうか。
魚のにおいは、ただの欠点ではなく、鮮度や扱い方のサインでもあります。
そして、正しい処理や工夫で大きく軽減できるものでもあります。
においの原因を知れば、魚の扱い方に自信が持てるようになり、
工夫をすれば、台所ににおいを残さず、美味しく魚を楽しむことができる――
魚との距離が、ぐっと近くなるはずです。
そして、魚忠のようなプロの手で仕立てられた魚なら、
においの心配を最小限にしながら、旨みと栄養をそのまま食卓へ届けてくれます。
魚は、体にやさしいだけでなく、毎日の食事に季節感やごちそう感を添えてくれる、とても奥深い食材です。
においを気にせず、気軽に、美味しく。
魚とのつきあいをもっと楽しんでいただけたら幸いです。
また次回も、魚にまつわるちょっと気になる話をお届けします。
お楽しみに。