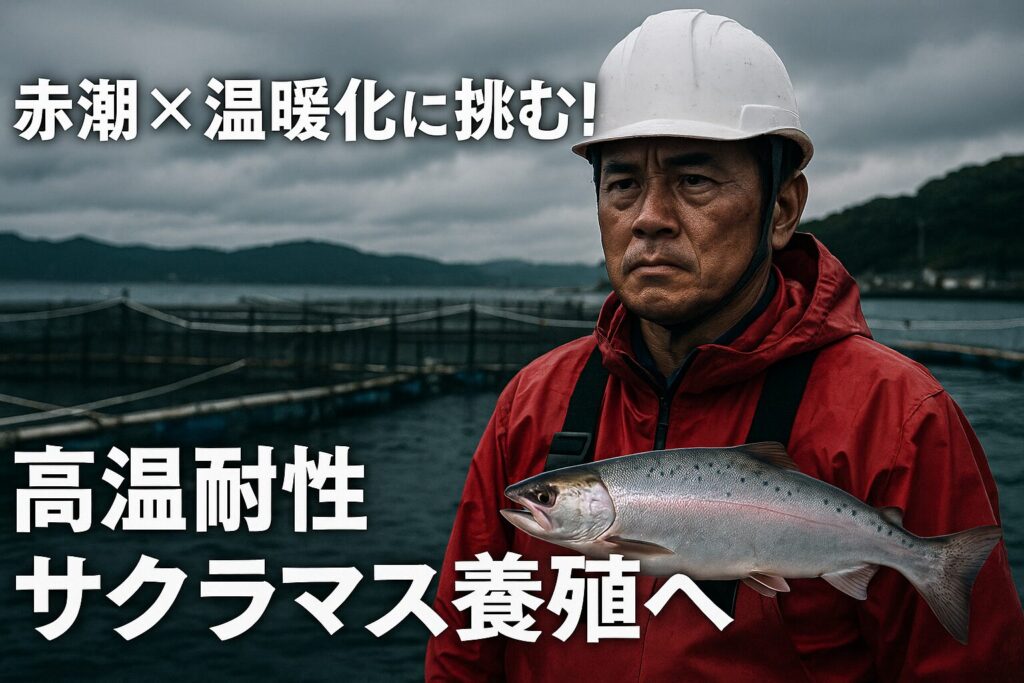
もくじ
はじめに
気候変動による海水温の上昇、そして赤潮の頻発――これらは今、海で魚を育てる「養殖業」に深刻な影響を及ぼしています。特に九州や西日本の沿岸地域では、かつてないほどの被害が相次いでおり、従来の魚種だけでは持続可能な養殖経営が難しくなりつつあります。
こうした中、長崎県の昌陽水産が新たに導入を進めているのが、「高温・赤潮耐性」を持つサクラマスの養殖です。この取り組みは、ただの新魚種導入ではなく、気候変動に対応する“次世代型養殖モデル”として注目されています。
本記事では、気候変動が水産養殖に与える影響から始まり、昌陽水産が挑むサクラマスの導入背景、その期待と課題までを詳しく解説いたします。
第1章:気候変動×赤潮が水産養殖にもたらす脅威
■ 養殖現場を直撃する「高水温」と「赤潮」
かつては安定的な収益源として期待されてきた水産養殖ですが、ここ数年でその前提が大きく揺らいでいます。最も大きな変化は、気候変動による海水温の上昇と、それに伴う赤潮発生の増加です。
赤潮とは、植物プランクトンの異常増殖により海水が変色し、魚介類に酸欠や毒素による被害を与える現象です。水温が高い夏から秋にかけて発生しやすく、養殖魚にとってはまさに“死の水”とも言える存在です。
さらに近年の赤潮は、従来と異なる高濃度・広範囲・長期間型が増えており、養殖業者にとっては避けがたいリスクになっています。
■ 被害の現実:一夜にして失われる魚たち
赤潮による被害は、魚が数時間のうちに大量死するという深刻なものです。2021年には九州北部で赤潮による大規模死滅が発生し、数十万匹規模の魚が全滅。数千万円から数億円規模の損失が発生しました。
加えて、夏季の高水温そのものも、魚の体調悪化や成長不良を招く要因となり、結果的に出荷遅延や歩留まり悪化につながっています。
特にサケ・マス類は冷水性の魚であり、従来は夏季の養殖が困難でした。そのため、生産可能な時期は限られ、養殖効率に大きな制約がありました。
■ 養殖業の存続が問われる時代へ
これらの状況により、水産養殖業は今、“環境変化に耐えうる新たな魚種・育成技術”の開発が急務とされています。単に設備を強化するだけでは対応しきれない課題に直面し、業界全体が変革の必要性を強く感じているのです。
こうした背景の中で、昌陽水産が導入を始めた「高温・赤潮耐性サクラマス」は、まさにこの転換期における新たな挑戦の象徴となるでしょう。
第2章:昌陽水産が導入する高温・赤潮耐性サクラマスとは?
■ なぜサクラマスなのか?
サクラマスは、本来冷たい海域に生息する魚で、養殖対象としては東北や北海道などの北日本が中心でした。しかし、近年の育種技術や飼育環境の改良により、高水温への耐性を持つ系統が開発され始めたことが、大きな転機となっています。
昌陽水産が導入を進めているのは、特に高温期(夏場)でも生存率と成長性能を維持しやすい系統で、これまで養殖のオフシーズンとされていた時期でも管理が可能となる見込みです。
■ 赤潮への耐性も期待される育種技術
さらに注目されるのが、赤潮への一定の耐性を持たせた育種個体の活用です。赤潮プランクトンへの耐性とは、魚体の粘膜防御機能や呼吸器官の耐性強化により、毒素の影響を受けにくくするというアプローチです。
これまで赤潮が発生すれば“網の中で大量死”というのが常態でしたが、耐性系統の導入により、被害を軽減できる可能性が見え始めています。
■ 養殖期間の拡大=収益チャンスの増大
従来、サクラマスの養殖は春から初夏にかけての短期間限定でしたが、高温耐性があることで夏場も飼育継続が可能となり、結果として出荷時期の分散や増量が見込めます。
これにより、以下のような収益面でのメリットが生まれます:
- 出荷時期をずらすことで価格の高い時期を狙える
- 年間出荷量を増やすことで単位面積あたりの利益を向上
- 養殖設備を季節ごとに転用せずに通年稼働できる効率性の向上
■ 「地産地消ブランド」としての可能性
昌陽水産では、養殖したサクラマスを県内のスーパーマーケットや直売所で販売することを視野に入れており、“長崎産サクラマス”という新たな地産ブランドの確立を目指しています。
地域住民にとっては新しい地元食材として受け入れられやすく、飲食店や学校給食など、地産地消モデルにも貢献することが期待されています。すでに試験出荷されたサクラマスについては、「クセが少なく脂がのっている」と好評の声も上がっているそうです。
■ 持続可能な水産業のモデルへ
このように、高温・赤潮耐性を備えたサクラマス養殖は、環境変化に強く、地域に根ざした持続可能な水産業モデルとして、将来的な広がりが期待される取り組みです。次章では、その可能性をさらに広げるために立ちはだかる課題と、それに向けた展望について解説していきます。
第3章:実現する共通メリット──養殖期間延長・地産地消ブランド化
■ 養殖期間の延長がもたらす経済的効果
高温耐性を持つサクラマスを導入する最大のメリットの一つは、養殖可能期間の大幅な延長です。従来は春から初夏までの限られた期間しか飼育できなかったため、収益の柱としては季節要因に左右されやすいものでした。
しかし、耐性系統により夏場も含めた長期間飼育が可能になることで、次のようなメリットが生まれます:
- 年間出荷体制の構築によって、収入の安定化
- 価格が高騰する時期への出荷調整で利益最大化
- 飼育設備の稼働率向上により投資回収効率の改善
つまり、一年を通じて戦略的に「育てて、売る」ことができるようになり、経営体力を強化できるのです。
■ 地元で育て、地元で売る「地産地消ブランド」へ
昌陽水産が狙うもう一つの柱が、“地元で育てて、地元で売る”という地産地消型の展開です。すでに長崎県内のスーパーマーケット数店舗で販売が始まっており、地域住民の関心も高まっています。
これは単なる「ローカル食材」ではなく、以下のような効果が期待されています:
- 安心・安全な魚を地域に提供し、食育や健康意識の向上に貢献
- 地元経済への還元効果(地元販売=輸送・保管コスト低減)
- 環境負荷の低減(長距離輸送が不要)
さらに、「長崎産サクラマス」という明確なブランドが確立されれば、飲食店や百貨店、高付加価値ECなどへの展開も見込まれ、ブランド力は県外へ波及していく可能性があります。
■ 持続可能性のアピールによる消費者支持
高温・赤潮耐性という特性は、気候変動に配慮した養殖=持続可能な漁業としても強いメッセージを持っています。現在、食品選びにおいて「環境配慮」や「SDGsへの貢献」を重視する消費者も増えており、そうした層への訴求力も非常に高いと言えます。
- 「地元の気候変動に対応した魚」
- 「未来の子どもたちに残せる水産資源」
こうした視点からの発信は、地域ブランドとしての価値をさらに高めてくれるでしょう。
第4章:商業化への課題と今後の展望
■ スケール拡大に向けた最大の壁:「赤潮耐性の実証と安定供給」
昌陽水産が導入を進める高温耐性サクラマスは、あくまでも先行的な試験導入段階にあり、商業ベースでの安定的な生産・供給体制の確立にはまだ時間と検証が必要です。
特に課題となるのが、赤潮への実効的な耐性の再現性です。水温や赤潮の発生条件は年ごとに異なり、「ある年は問題なかったが、別の年には被害が出た」というリスクも想定されます。
そのためには、
- 長期的なフィールドテスト
- 複数年・複数地点での育成比較
- 生存率・成長率の定量的データ化
などを通じて、実証性のある“耐性品種”としての確立が求められています。
■ 餌設計と水温管理技術のブラッシュアップ
高水温に耐える魚であっても、その成長と品質を最大限に引き出すためには、最適な餌と飼育条件の設計が欠かせません。
現場ではすでに「夏場に食欲が落ちやすい」「脂のノリにバラつきが出る」といった課題も報告されており、
- 高水温期に適した高エネルギー飼料の開発
- 給餌タイミングの最適化(夜間給餌など)
- 小型水温緩和装置の併用による環境安定化
といった技術的サポートが、今後の普及に向けた大きな要素となります。
■ 加工・販売ネットワークの整備も不可欠
育てるだけでは意味がありません。消費者の元へ確実に届けるためには、
- 県内外への販路開拓
- 加工・冷凍・パック詰め技術の標準化
- 物流体制(特に夏場)の強化
といった「売るための仕組みづくり」も重要です。特に水産品は鮮度が命。地元スーパーでの実績をもとに、全国の高級スーパーや外食業界との連携、さらにはECでの販売体制整備も今後の鍵となります。
■ 成功すれば全国展開のモデルに
このプロジェクトが成功すれば、昌陽水産は単なる「地域の養殖業者」から、「気候変動に対応するスマート養殖モデルの先駆者」として全国に発信できる立場になります。
長崎発のこのモデルが、同様に赤潮被害や高水温に悩む他県の養殖業者に波及すれば、やがて日本全国の“次世代養殖の標準”となる可能性も十分にあります。
そのためには、行政・大学・民間企業との連携強化、補助金・研究支援の継続、そして現場の声を活かした実践的な技術普及が不可欠です。
おわりに
気候変動が水産業に与える影響は、年々深刻さを増しています。赤潮、高水温、魚の大量死――それらはすべて、海と共に生きる私たちへの“問いかけ”でもあります。
長崎・昌陽水産による高温耐性サクラマスの導入は、こうした環境変化と真正面から向き合う、まさに挑戦的な第一歩です。育てる魚を変え、育てる方法を変え、売る仕組みまでをも含めた“未来型の養殖モデル”。この取り組みが成功すれば、全国の養殖業に新しい道筋を照らす存在になることでしょう。
自然と共に生きる。未来を育てる。養殖業は今、次のステージへと動き出しています。
魚忠ECサイトのご紹介
魚忠では、こうした次世代の水産養殖が生み出す“安心・安全・おいしい魚”を、皆さまの食卓へお届けしています。
創業70年以上の老舗魚屋として、全国の信頼できる生産者から仕入れた、選りすぐりの魚介を毎日取り揃えています。
気候変動に負けない、新しい魚のカタチ。
それを感じられるのが、魚忠の魚です。
ぜひ、当店のオンラインショップをご覧ください。
👉 魚忠オンラインショップはこちら
https://uochu.base.shop/
